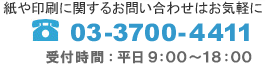紙の基礎知識
- 洋紙
日本での製紙工業の始まりは、明治5年(1872)に渋沢栄一によって「抄紙会社」という名の製紙会社が設立されてからで、「日本紙業総覧」によれば、明治7年洋紙製造高35,000ポンド(約16トン)の表記があります。
この時の洋紙輸入高は、705万8070ポンド(約3100トン)です。明治6・7年までは、すべての用途に対して、紙は「和紙」で賄われていました。
この頃に「洋紙」という言葉が使われ始めたと思われます。当初、舶来洋紙、輸入洋紙、西洋紙と呼ばれ、明治6・7年に製造開始された国産紙を国産洋紙、西洋紙と呼ばれたようです。
洋紙は、和紙に対応する言葉として使われていますが、「西洋(欧米)で発展した紙で、機械で抄造され、パルプ(主に木材)を原料にした紙で、一部、木綿、亜麻、エスパルトなどのパルプも使われる」といったところでしょうか。
- 和紙
JISの紙・板紙及びパルプ用語によると、和紙は、「我が国で発展してきた特有の紙の総称。手すき和紙と機械すき和紙とに分類される。
本来は、じん皮繊維にねりを用い、手透き法によって製造された紙。
現在は化学パルプを用い、機械すき法によるものが多い」と解説されています。
- 用紙
「用紙」は、「ある特定の目的に用いる、型の決まった紙」(辞林21)のことで、印刷用紙、筆記用紙、図画用紙、情報記録用紙、原稿用紙、メモ用紙まで沢山あります。何らかの使用に供する紙で、使用目的を示す場合に限って使われているようです。
- 紙の定義
「紙」という字は、漢字の語源から蚕糸(絹)を寄り合わせる形を表す糸偏と、匙のように薄く平らで柔らかいことを表す氏旁からなっていて、言葉の意味から繊維で出来た薄い物、と言えるでしょう。
「カミ」と発音されるようになったのは、奈良時代に入ってからです。
語源を特定できない難語のひとつですが、樺の木の皮から、カバ⇒カビ⇒カミと音韻が変化したものか、あるいは木簡の簡からカミに転韻したものと推察されています(「紙の今昔」)。紙の定義という点では、「植物繊維その他の繊維を絡み合わせ、こう着させて作ったもの。
尚、広義には素材として、合成高分子物質を使用して作った合成紙、合成繊維紙、合成パルプ紙の他、繊維状無機材料を配合した紙も含む」(「紙パルプ事典」。JIS P 0001-4005-参照)となります。
これを言い換えると「木や草の繊維を水の中でバラバラにして、網目などを使って脱水しながら薄いシートを作り、これを乾かしたもの」となります。この時、水の作用と繊維の性質から繊維同士が結合して強度がでます。
繊維と繊維が交叉したところで接着することが紙の強さの大きな要因になっています。
日本語でも英語でも紙は、薄いものの喩えに使われます。「紙のように薄い…」「人情 紙の如し」等々。
- パルプの定義
パルプは、「木材その他の植物を機械的、または科学的処理によって抽出したセルロース繊維の集合体で、紙、レーヨン、セロハンなどの原料である。
製法により、機械パルプ、化学パルプなど、用途により製紙用パルプ、溶解パルプなどに分類される。」(JIS P0001-1012-参照)ものということになります。
身近なもので置き換えてみますと、木材を、ポテトチップのように削ぐように小さく切って、このチップを機械や熱や水やアルカリの力で処理しますと、バラバラになった小さな繊維の集まりができます。
これを「パルプ」といいます。パルプが水に混ざった状態は、お粥にそっくりです。パルプは、pulpと書きますが、桃の果肉のような柔らかいかたまりのことで、コーヒーの赤い実から果肉をとりコーヒー豆にすることもパルプといいますし、歯医者さんは歯髄をパルプといいます。
何となく柔らかそうなイメージが、パルプのようです。
昔はパルプに適した樹種がありましたが、その後、広葉樹を含めていろいろな木からパルプが作られるようになりました。
パルプにする方法も、グラインダーですり潰す機械パルプ(GP)、サルファイトパルプ(SP)、クラフトパルプ(KP)など各種あり、多くのパルプは漂白されます。
- 紙の表と裏
製紙の場合は、金網からプラスチック製の網(製紙業界では、何故かこの網のことをワイヤーと呼ぶため、プラスチックワイヤーと称します)に変っても、手漉きの頃と変わらずに紙を抄いています。
つまりパルプの水分散液からワイヤーの下に水を抜いて、ワイヤーの上にマット(シート)を作ります。この後、さらにプレスして水を絞り、シリンダードライヤーで乾燥して紙を作ります。
この時、ワイヤーを横から見ていると想像して下さい。
ワイヤーの上にスポンジ状のパルプマットが乗っています。
ワイヤーに接しているところや、その少し上の辺りは、ワイヤーの目から水が下に抜けるときに、細かい繊維その他が抜けてしまうので、粗い構造となります。
上の方は、緻密な構造になって、どちらかというと滑らかな感じです。基本的には、このワイヤーで作られる紙の構造の違いが、後の工程でもずっと保持されたまま紙となり、紙になったときもこの性質が現れます。
これを紙の表と裏、その差を表裏差といいます。通常、ワイヤーに接している側の粗い構造面をワイヤーサイド、もしくは裏といい、反対側の緻密な面をトップサイド、もしくは表といいます。
またトップサイドは、プレス工程でフェルトに当たるので、別名フェルトサイドともいいます。
紙を作るときは、必要に応じて白さや不透明性を向上させるため、槇料と呼ばれる鉱物質の白い粉や、染料、顔料なども使いますが、これらも抄紙の時のワイヤーの目から一部抜け落ちます。
このため、パルプ繊維で作られる構造の粗さだけでなく、槇料や染料も紙の表と裏では多少差がでてきます。
表裏差は平滑性や色、さらに極端な場合には印刷適正にまで現れます。
また、繊維の並び方を見ても、紙の表はランダムで、紙の裏は配向が強く、カールなどにも影響します。コート紙などの場合は、表裏差がほとんどないように作られています。
エンボスやキャストコートなどの加工によっては、その使用目的に合った面を表と称する場合があります。
最近では、これら表裏差をなくすために、2枚のワイヤーで挟むようにして、両面から脱水することが行われています。
この場合、両面とも表あるいは裏となって、構造的な表裏差は少なくなっています。
- 紙のタテとヨコ(紙の目)
紙には、タテ目とかヨコ目と呼ばれる"目"があります。
目という言葉には、細かく一列に並んだもののすき間の意味があり、木目、板の柾目といった使われ方をします。
紙の場合も、これに近い意味で使われます。水の中にパルプ繊維(木の繊維の集まり)を混ぜ、金網で水を下に抜くと、パルプ繊維が並んだ薄いシートができます。
これを機械で連続して行う時、パルプ繊維は抄紙機の流れに乗って進んでいきます。
つまり、パルプ繊維が紙のできる方向に向いているため、紙の目となり、この方向をタテ目といいます。用紙にした場合、長辺方向が紙の進行方向=紙の目の方向となっているものをタテ目の紙といい、四六判の場合、788×1091mmと表記します。(はじめの数字が目と直行方向の寸法を表わします。)
では、ヨコ目はというと、紙の進行方面は変えられませんので、用紙を裁断するときに、長辺が進行方向と直角になるように断裁して作ります。
断裁した後に、紙を90度回転させると、紙の目が横を向いた用紙になります。
四六判の場合、1091×788mmと表記します。用紙を注文すると時、指示を受けるとき、どちらの数字が先に来るかで目が変わります。
この用紙の目は印刷物、特に本を作るときにはとても重要です。
特別な場合を除いて、本を立て時の上下方向が、紙の目に向いている方向になるようにします。
そうすることにより、頁のめくりやすさやおさまりがよくなるだけでなく、製本する場合などにとても都合よくなります。
- 紙の目取りと面つけ
作ろうとする本や印刷物の大きさ、判型が決まったら、最適な(無駄の無い)原紙が決まります。
基本的には、A系列はA判、B系列はB判というように、同じ系列の原紙になります。
次いで使用する印刷機に合わせて、倍判、全判、半裁に面付けを決めます。
この時、裁ち落とし、くわえ、くわえ尻、針先、針尻の分を考慮します。例えば、A5判の本を全判で16取り(表裏両面で32頁)の面付けをする場合、2頁が1製版寸法になり、本の天地方向が用紙のタテ目になるようにしますので、用紙はA全判もしくは菊全判のタテ目に面付けするとむだなく取れます。
同様にB5判の本を作る場合は、B全判もしくは四六判のタテ目に面付けすると無駄なく取れます。
全判の場合、このような書籍や印刷物の判型が奇数はタテ目、偶数はヨコ目と覚えておくといいでしょう。
※本項は、株式会社美術出版社刊「紙の大百科」中の原 啓志氏著「知って得する紙の基礎知識」の一部を引用させていただきました。